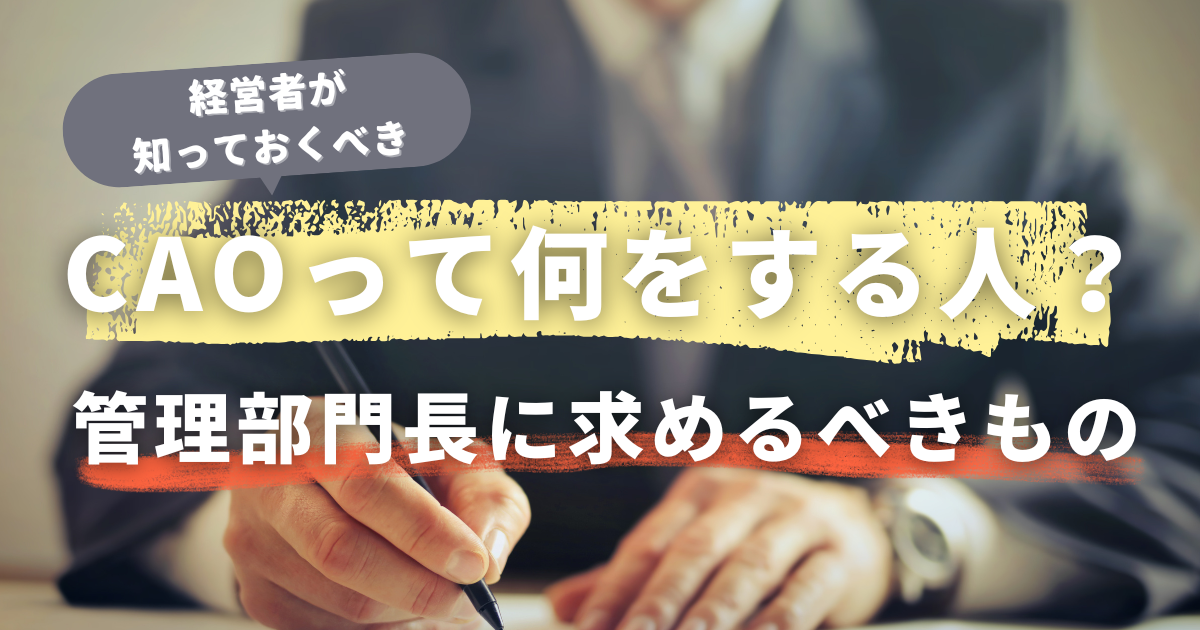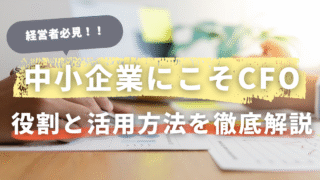はじめに
人材不足、法改正、急激な外部環境の変化──。現代の経営はかつてないほどのスピードと判断力を要求されています。特に中小企業にとっては、資金力・人材リソースの制約の中でどれだけ柔軟かつ的確に経営判断を行えるかが、今後の生き残りを左右するといっても過言ではありません。
そのような環境のなか、企業の持続的な成長やトラブル回避のためには、「経営の屋台骨」となる管理部門の整備が急務です。管理部門とは、経理・財務・労務・法務・総務など、直接的な売上に結びつかないけれど、企業運営の安定を支える重要な機能を担う部署です。しかしながら、多くの中小企業では、売上を立てる営業や現場に比べて後回しにされる傾向があります。
こうした状況のなか、最近注目されているのが「CAO(Chief Administrative Officer:最高管理(統括)責任者)」というポジションです。経営者に代わって、または並走しながら管理体制を整える専門的な役割として、大企業だけでなく中小企業においてもその存在意義が見直されています。
また、CAOは経営者にとっての「右腕」ともいえる存在であり、現場に任せきりにしていた管理部門の問題を浮き彫りにし、必要な改革を立案・実行してくれる重要なポジションでもあります。社内の各部門との橋渡しを担い、部門間の連携や業務効率の改善にも大きく貢献することが期待されます。
本記事では、CAOとは何か? なぜ今中小企業にもCAOが必要とされているのか? そして、資金に限りのある中小企業にとって現実的な導入方法としての「業務委託」という選択肢について、詳しく解説していきます。
CAOとは何か?管理部長・経理部長との違いとその役割や責任範囲
「CAO(Chief Administrative Officer)」とは、直訳すれば「最高管理(統括)責任者」。企業活動の基盤を支える管理業務全般の責任者です。特に以下のような領域において、統括・改善・戦略的な意思決定支援を行います。
役割と責任範囲
経理・財務領域
月次・年次決算、キャッシュフローの最適化、資金繰りの予測と管理、金融機関との折衝など。経営の「数字」を的確に把握し、未来を見据えた財務戦略を構築する役割を果たします。税務申告や資金調達の戦略立案も、経営にとっては欠かせない項目です。
人事・労務領域
採用・退職対応、就業規則の整備、社会保険手続き、勤怠管理、労務トラブル対応。人材の定着と成長を図るため、制度整備や働きやすい環境づくりにも関与します。近年ではハラスメント対策やメンタルヘルス対応など、労務リスクへの備えも重要です。
総務・法務領域
契約書の確認・管理、各種許認可、社内規程の整備、株主総会や取締役会の運営など。法律トラブルを未然に防ぎ、円滑な事業運営を支えるバックオフィス体制を築きます。法改正への対応もスピーディに行う必要があります。
リスクマネジメント
コンプライアンス体制の整備、情報管理、内部統制の導入など。デジタル化や外部委託の進展に伴い、情報セキュリティやデータ保護も重要な任務です。内部監査体制の構築によって、不正防止や企業価値の維持にも貢献します。
管理部長や経理部長との違いは?
つまり、CAOは単なる「事務責任者」ではなく、企業の健全な経営基盤を築くための「戦略的管理部門責任者」であり、経営者のビジョンを具現化するための中核的存在なのです。実業務としては、中小企業の管理部長と役割は酷似しており、マネジメントのみならず前述したような業務内容、特に経理関連の業務において自ら手を動かしCEO(社長)やCFOへの橋渡しを行うようなポジションと考えて相違ありません。
CFOについては以下の記事を参照ください
なぜ今、中小企業にCAOが求められるのか?
中小企業の経営環境は年々厳しさを増しています。デジタル技術の進展、法令遵守(コンプライアンス)に対する社会的要請の高まり、さらには働き方改革や人的資本経営の推進といった新しい経営テーマに対応する必要があり、経営者が単独で把握・対応するには限界があります。
特に問題なのは、「何がリスクなのかすら把握できていない」状態が、多くの中小企業で見受けられる点です。例えば、就業規則が古いまま放置されていたり、税務署や年金事務所からの調査に十分な資料を準備できていなかったり、情報漏洩対策が全く講じられていなかったり──これらはすべて、管理体制が不十分なことによって引き起こされる潜在的なトラブルです。
また、事業の拡大や採用人数の増加により、社内ルールや仕組みが「属人化」したまま放置されているケースも少なくありません。創業期には通用していたルールも、従業員数が10名を超えたあたりから混乱を招きはじめます。そのタイミングで経営者が現場と管理を両立し続けるのは、極めて困難です。
このような背景から、「管理部門を見直すこと=経営戦略の要」と捉える必要が出てきました。ここに、CAOというポジションの必要性が浮かび上がります。経営者の代わりに「全体を見渡す目」を持ち、経理・労務・法務といった各領域の専門家と連携をとりながら社内体制を整えることで、経営判断のスピードと精度を飛躍的に向上させることができます。
つまり、CAOの存在は「攻めの経営」を下支えする「守りの強化」とも言えます。外部環境が不安定な今だからこそ、CAOによって管理基盤を強化し、持続可能な経営体制を構築することが求められているのです。
CAOを雇うことの現実的な課題
では「今すぐCAOを採用しよう」と考えても、中小企業にとっては現実的なハードルがいくつも存在します。
まず最大の課題は「人件費」です。CAOは本来、豊富な実務経験と広範な知識を持ったハイレベルな人材であり、その報酬水準は決して低くありません。正社員としてフルタイムで雇用するとなれば、年収800万〜1,500万円程度のコストを見込む必要があります。この金額は、多くの中小企業にとって負担が大きく、現実的ではないケースがほとんどです。
さらに、そうしたハイスキル人材を「そもそも採用できるのか」という問題もあります。現在の人材市場では、管理系のプロフェッショナルは大企業や外資系企業に集中しており、中小企業が自力でリクルートするには相当な工夫とコネクションが必要です。
加えて、仮に採用できたとしても「その人材を活かしきれるかどうか」も別問題です。管理体制が未整備の企業では、CAOが入っても指示系統があいまいであったり、経営者との役割分担が明確でなかったりすることで、機能不全に陥ることがあります。せっかくの高コスト人材を十分に活用できず、最悪の場合は入社後すぐ退職するなどの事態に陥る事もあり、そうなってしまっては本末転倒です。
このように、「CAOの重要性はわかるけれど、現実には難しい」というジレンマを抱えている中小企業は少なくありません。そこで注目されているのが、次に紹介する「外部CAO」という柔軟な選択肢です。
「外部CAO」という新しい選択肢
前述したように、常勤のCAOを雇うのは人件費の面でもハードルが高く、現実的ではないという企業が大半でしょう。そこで近年注目されているのが「外部CAO(業務委託CAO)」という選択肢です。
外部CAOとは、専門家や専門企業に対してCAO業務をアウトソーシングする仕組みです。必要な時に、必要な分だけ、プロフェッショナルの知見と手を借りられるため、常勤の管理職を抱えるよりも大幅なコスト削減が可能になります。
また、外部の視点を持つことで、組織の問題点や改善点が浮き彫りになりやすく、内部人材では気づきにくい課題への対応も期待できます。具体的には以下のような活用が可能です。
- 月1回の経営会議に参加し、経営者と一緒に管理部門の課題を整理・分析
- 業務改善プロジェクトを立ち上げ、社内チームとともに遂行
- 人事制度や就業規則の見直しなど、専門知識が必要な改革を短期で遂行
- 労務・法務・経理など、委託先との橋渡し役としての調整業務
このように、外部CAOは「社外にいながら、社内の右腕」や「週に1回来てくれる管理部門の長」として、非常に柔軟かつ実効性の高い選択肢となります。
外部CAO導入のメリットと注意点
外部CAOを導入することによって得られるメリットは多岐にわたります。
主なメリット
- コストの最適化:常勤雇用に比べて人件費を抑えられる。
- 専門性の確保:複数の企業を支援してきた実績から、広範な知見を活かせる。
- スピーディな改善:既にノウハウを持っているため、業務改革のスピードが速い。
- 経営者の意思決定支援:社内に忖度のない第三者として、冷静な意見を提示できる。
このように、採用や内部昇格に比べるとコスト面に限らず大きなメリットを享受できます。
注意点
一方で、少なからず注意点(デメリット)は存在することは念頭に置く必要があります。
- 導入初期には社内の業務内容や文化を理解するまでに一定の時間を要する
- 社員からの抵抗感(「外部の人に何がわかるのか?」という心理)への配慮が必要
- 外注先によって品質や対応範囲にバラつきがあるため、慎重な選定が必要
そのため、導入にあたっては「経営者のビジョンを理解し、寄り添ってくれるパートナー」を見つけることが成功の鍵となります。
まとめ:中小企業こそ「右腕」を持つべき時代
これまで述べてきたように、経営を継続的かつ安定的に行うためには、管理部門の整備は不可欠です。とはいえ限られたリソースの中で、すべてを自社内で完結するのは現実的ではありません。
そうしたなかで、外部の力をうまく取り入れる「外部CAO」という選択肢は、非常に有効です。
経営者が本業に集中するためにも、会社の屋台骨を支える管理部門を外部のプロに任せるという視点を、今こそ真剣に検討すべき時期ではないでしょうか。
弊社は最終的なゴールを自社での経理業務完結、「経理の内製化」とする会社を全面的にサポートします。経営基盤の構築段階や内部統制の強化といったどのようなフェーズであってもサポートも可能です。
まさに今回ご紹介した様なCAO業務として、業務フローの見直しや経営者にとって有用な管理会計の構築、既存のシステム利用はもちろん、新たなICTの導入についても一緒に行います。また既存社員の育成や、新たな人材採用に必要な募集要項作成から面接に至るまで、ワンストップでサポート致します。
是非一度ご相談ください。