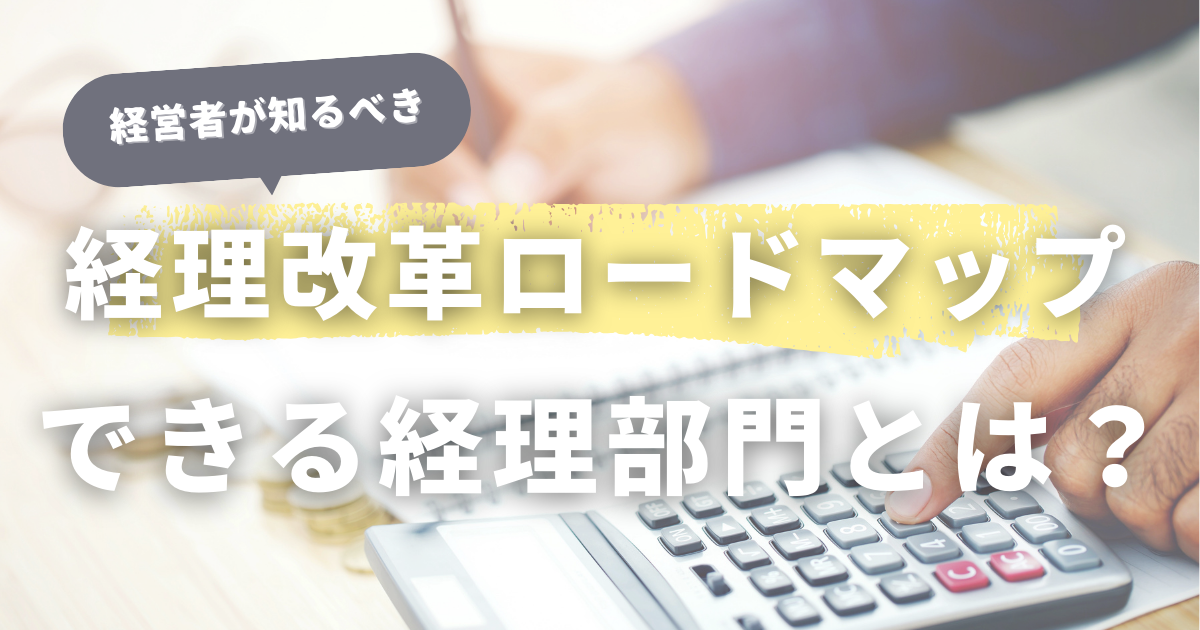問題提起:
多くの中小企業では、経理業務が属人的で非効率なまま放置されがちです。手作業が多く、ミスが発生しやすい環境では、経営判断に必要な正確な数値が即座に把握できません。経理部門の改革を進めなければ、事業の成長や資金管理に悪影響を及ぼす可能性があります。
記事を読んでわかること:
経理業務を効率化するための具体的なステップ、適切なツールの導入方法、そして「できる経理部門」を構築するためのポイントを解説します。
記事を読むメリット:
経理業務を効率化し、コスト削減や経営の可視化に最適な方法を考えるヒントを得ることができます。さらに、経理部門の生産性向上により、企業全体の競争力を高める参考になるでしょう。
経理部門の役割と重要性
経理部門は、企業の財務状況を正確に把握し、適切な資金管理を行う中枢的な役割を担っています。具体的には、日々の取引の記録、財務諸表の作成、税務申告、予算管理など、多岐にわたる業務を担当します。予算管理などに関しては経営企画が担う事が多いものでもありますが、今回はその点も併せて解説をしていきます。
経理の重要性とは?
経理は単なる数字の記録ではなく、企業の経営判断を支える基礎となる情報を管理する役割を果たします。具体的には過去の成果(損益計算書)から現在のお金の状況(貸借対照表)を把握するための重要な資料を作成する事にあります。経理は主に過去の数字的データを取りまとめることが主要な仕事と言えますが、これらを早く正確に取りまとめる事で、経営者は経営判断にあたり有用な情報を得ることができます。
その上で例えば、
- 資金管理: キャッシュフローの健全化を図り、資金繰りのトラブルを防ぐ
- 税務管理: 適切な税務処理を行い、法令違反や不要な税負担を回避する
- 財務分析: 損益分析やコスト削減を行い、経営戦略をサポートする
これらの役割を財務や経営企画の部署と連携し作成・分析することで、経営者はさらに正確な情報に基づいた意思決定が可能となり、企業の健全な運営が実現します。
経理業務を税理士に任せるのはダメなのか?
経理業務を税理士に任せることが必ずしもデメリットになる訳ではありません。もし社内に経理人材がいない場合、新たに経理の採用を考えると確実にコスト増に繋がります。税理士に任せられる状況であれば、人員を1名採用するよりは安く、最低でも年に1回の決算申告は対応してくれるかと思います。
しかし、ある程度の規模感の会社になってきているのであれば、前述したような財務的な側面の会社の状態をなるべくタイムリーに把握することで、顧客開拓や新事業の構築に繋がる事も少なくないでしょう。こういった点も踏まえて、自社の状況に併せて適切なタイミングで経理部門の構築を始めることを推奨します。
経理業務のステップと全体像
上記のような体制を整え、ビジネスを進めていくためには経理部門の組織化が欠かせません。現在の経理部門、並びに管理部門の状況と照らし合わせて、経理業務を組織的に再構築するためのステップとして、次のような段階的な形で進めると良いでしょう。
第1段階: 社内で月次決算を行える体制を構築
多くの中小企業では、経理業務を税理士や外部業者に丸投げしているケースが見られます。しかし、社内での月次決算ができるようになることで、リアルタイムで会社の財務状況を把握でき、経営の判断が迅速になります。
- 最初に取り組むべきこと
- 経理担当者の選定(または既存スタッフの育成)
- 会計ソフトの導入と基本的な運用ルールの確立
- 領収書や請求書の整理方法を統一
- 資金繰り表の作成と更新
経理未経験、簿記の資格などもない既存のスタッフから経理担当者を育成する場合、いきなり月次決算を目標にすると、レベルが高すぎて精神的な負担が大きいと考えられます。その場合はまず、請求書や領収書などの資料の取りまとめと、勘定科目の理解を進める事をスタートにするのが良いでしょう。また、クラウド会計ソフトを導入することで、簿記の知識がなくても基本的な処理が可能となります。この場合はスタート時点の会計ソフト導入が肝となるため、一時的なコンサルティングの利用を検討するのも良いかもしれません。
第2段階: 年度決算を社内で実施し、財務管理を強化
年度決算は、税務申告や経営計画の策定に不可欠です。社内で正確な決算業務を行えるようにすることで、より戦略的な財務管理が可能になります。
- この段階で行うべきこと:
- 年次決算が可能なレベルの社員の採用または育成
- 会計データの正確な記帳(決算特有の処理を含む)
- 決算書(貸借対照表・損益計算書)の作成・チェック
- 税理士との連携を強化し、正確な税務申告を実施
会社の方針によるところかと思いますが、私は必ずしもこの段階で、社内で申告書の作成スキルが必要であるとは思いません。経営者にとって意思決定にたる有用な情報は税引前当期純利益の時点で、ある程度把握可能であり、それをもって戦略を考える事が可能だからです。またプロである税理士に任せることで、チェック機能を果たすことも期待でき、経理担当者の精神的負担の軽減にも繋がる事が期待できるためです。
第3段階: 管理会計を導入し、経営戦略に活用
このステップであると管理会計を取り入れることで、単なる数字の管理ではなく、企業の成長戦略に直結する情報を活用できます。その際、損益計算書の計上基準を現金の出入りで管理する現金主義から、実際に売上や費用が発生した発生主義(実現主義)の考え方に切り替えることで、より適切な期間損益を把握することができるようになります。管理会計は財務や経営企画の部署が担う事が多いため、不在の場合はそちらの組織化も含めて検討しつつ、取り組むと良いでしょう。
- 取り組むべき事項:
- 部門の管理者の設置及び、経営企画や財務担当者などの人材登用
- 発生主義の採用と予実管理を導入し、経営計画の精度を向上
- 部門別損益管理を行い、利益率の高い事業を明確化
- 財務指標を活用し、経営リスクの把握と改善策の策定
発生主義や管理会計の導入を進める上では会社の組織化が重要です。資料の取りまとめを始めとしたルールをしっかり策定し、内部統制を強化する事で、計上漏れや月次ズレを防ぐことができます。またより精度の高い管理会計情報の作成には、会計的な数値データのみならず、非財務データと呼ばれる採用計画や売上計画の根拠となるような顧客構造やマーケティングの計画などさまざまな情報も必要となってきます。
第4段階: IPOにも対応できる、税務会計ではない財務会計の導入
中小企業の経理を考える上で、このステップは必ずしも全ての会社が目指すべき段階ではないと思います。しかしながら、企業会計原則に則った、財務会計にも対応し得る体制を構築することは、より適切な企業の状況を把握することができるようになることはもちろん、経営者にとってはイグジットを考える上でも必要となる可能性もあります。
- 必要になるであろう取り組み:
- 財務会計に精通した人員及び責任者の登用
- 財務と会計の分離
- 内部統制の構築
- 開示に併せた決算の早期化と資料の作成
この段階においては全てが内製化されている必要があるように思われるかもしれません。ですが、例えば、経理業務の記帳作業や内部監査など一部の業務は外部利用が可能です。
ただし、責任者などに関しては自社にフルコミットしている事が求められるのが通例です。
経理部門の主な業務内容
経理部門の業務は多岐にわたりますが、大きく以下のように分類できます。
日常業務
経理の基本的な業務になります。会社によって範囲はまちまちですが、前述した第1段階ステップの会社であっても、最低限、現金出納帳管理と経費精算の取りまとめはできる状況を構築する必要があると考えられます。
- 仕訳入力:すべての取引を会計ソフトに入力し、財務データの正確性を確保する
- 現金出納管理:企業の現金の流れを把握し、適切な管理を行う
- 売掛金・買掛金の管理:取引先との入出金の確認を行い、未回収の債権を防ぐ
- 経費精算:社員の経費を適切に処理し、経費負担の透明性を確保する
月次業務
資金繰り表の作成と予算実績の比較は財務や経営企画の業務内容になるところではありますが、経理がこの範囲までできる状況にあると、経営者は経営判断に有用な情報として利用することができるようになります。
- 月次決算の実施:正確な財務状況を毎月把握し、適切な意思決定を支援
- 試算表の作成:経営者向けに分かりやすい財務レポートを作成
- 資金繰り表の作成:企業のキャッシュフローを明確化し、資金計画を立てる
- 予算と実績の比較分析:目標と実際の収益・支出を比較し、改善点を見つける
年次業務(年に1回の業務も含む)
月次決算の精度が高いと、年次決算業務は比較的スムーズに作業が行われます。ですが、棚卸など月次では中々行えない業務も併せて確認する必要があります。また税務申告はもちろん、法定調書の作成や法人税の納付などを期日までに行う必要があります。
- 決算整理仕訳:棚卸資産の評価、経過勘定や減価償却の確認など
- 年度決算:企業の財務状況を総括し、貸借対照表や損益計算書を作成
- 税務申告: 法人税、消費税、固定資産税などの計算と申告
- 法定調書の作成: 税務署へ提出する各種調書を正確に作成(1月末)
管理会計
財務や経営企画の担当者と協力し、予算や事業計画の作成に必要なデータを提供します。特に経理は月次や年次決算を通して、過去のデータを正確に取りまとめる事が重要です。
- 予算策定と予実管理:事業計画に基づいた適切な予算を策定し、実績と比較
- 原価計算:各事業のコストを詳細に把握し、利益を最大化
- 経営分析:ROI(投資収益率)、ROE(自己資本利益率)、キャッシュフロー分析を活用し、経営の最適化を図る
経理業務効率化のポイント
経理業務を効率化することで、企業全体の生産性向上やコスト削減が可能になります。以下のポイントを押さえることで、よりスムーズな経理業務を実現できます。
業務の標準化
業務手順を統一し、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できるようにすることが重要です。
- マニュアルの作成と更新:業務手順を明確に記載し、新入社員や異動者でもスムーズに業務を行える環境を整えます。
- チェックリストの活用:重要な経理処理の漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
- 教育・研修の実施:定期的に社内研修を行い、業務の理解度を高めます。
ペーパーレス化
経理は在宅ワークがし難い業種です。一方で、紙の書類を減らし、デジタル化を推進することで、業務効率を大幅に向上させることができます。
- 電子帳簿保存法の活用:デジタル化を進め、法的要件を満たしながらペーパーレス化を実現
- クラウドストレージの活用:Google DriveやDropboxなどを利用し、どこからでも書類にアクセス可能に
- 電子契約の導入:紙の契約書のやり取りを減らし、手間とコストを削減
定期的な業務見直し
業務の効率化には、定期的な業務フローの見直しが不可欠です。特に組織構造や事業内容の変化、業務プロセスのそのものの変化は経理にも影響があるため、適宜見直しを行う事が重要です。
- 業務プロセスの可視化:フローチャートなどを用いて現状を把握。
- ボトルネックの特定と解消:業務の滞りや無駄を発見し、改善策を講じる。
- 業務分担の最適化:人員配置を見直し、適材適所を実現。
ITツールの活用による業務改善
近年、多くの経理業務がITツールによって自動化・効率化されています。適切なツールを導入することで、作業時間の短縮や人的ミスの防止が可能になります。
クラウド会計ソフトの活用
クラウド会計ソフトを導入することで、経理業務の負担を大幅な軽減が期待できます。
主なメリット
- リアルタイムでの財務状況把握:いつでもどこでもアクセス可能
- 自動仕訳機能:銀行口座やクレジットカードとAPI連携し、自動で仕訳を作成
- 税理士との連携が容易:クラウド上でデータ共有が可能
代表的なクラウド会計ソフト
経費精算システムの導入
経費精算システムを活用することで、従業員の経費処理の手間を削減し、業務効率を向上させることができます。
導入のメリット:
- 経費申請・承認のペーパーレス化:紙の節約やワークフローによるスピーディーな決裁が期待できます。
- スマホアプリで簡単に領収書をアップロード:紙での保管が不要となり、電子帳簿保存法の要件を満たす保存方法で資料管理ができるようになります。
- 会計ソフトとの自動連携:手作業での仕訳作業が不要になり、業務工数が削減可能になる。
代表的なツール
- ジョブカン
- Staple
- 楽楽精算
基幹システムの活用
基幹システムを導入すると、売り手としての発行・送付・入金管理の一元化が可能になる事はもちろん、それに紐づいた仕入の発注は支払FBデータの作成まで一貫して行うことができ、経理業務に限らず会社全般の業務が効率化されます。
導入のメリット
- 請求書作成の自動化:月次での請求書発行が効率化されます。
- 電子請求書の送付によるコスト削減:電子での請求書発行は郵便代の値上げに対応したコスト削減になり、先方側のデータ管理も楽になります。
- 発注・在庫管理の効率化:売上に基づいた発注業務が行えるため発注業務が後逸化し、在庫を持つ企業にとってはあるべき在庫数を把握する事ができます。
代表的なツール
- Misoca
- Bill One
- 楽楽明細
経理人材の育成と組織体制の構築
優秀な経理人材の確保と育成は、経理部門の質を高める上で非常に重要です。特に一定のスキル以上を保有する経理人材の採用が難しい昨今においては、育成による内部からの人材創出が重要なテーマともなっています。
経理人材の育成
経理担当者が最新の知識を持ち、正確な業務を遂行できるよう、継続的な教育が必要です。以下が育成のための計画一例です。
- 定期的な研修の実施:会計基準の変更や税法改正への対応力を強化。特に税法に関わる内容は外部研修を奨励し、最新の情報を入手する方法を構築する
- 資格取得支援制度:日商簿記2級以上の取得を推奨し、費用補助を行う。また経理はデータの取りまとめなどにExcelを多用することが多いため、そのための書籍補助なども有効である
- OJTの活用: 実際の業務を通じたスキル向上を図る。伴走者となるような外部協力者を採用し、実務を一緒に行う事でより早い能力向上が期待できる。
組織体制の構築
経理部門内での業務分担を明確にし、業務の効率化と内部統制の強化を図ります。
- 分業制の導入: 記帳、出納、税務などの業務を適切に分担。特に記帳と出納を分ける事は、社員による不正を防ぐ手段としても有効です。
- チェック体制の強化:ダブルチェックを徹底し、ミスを防止。単なる数字の確認ではなく、仕訳の内容確認を行えるレベルの人員が居ると尚良いです。
- 業務の可視化:フローチャートやタスク管理ツールを活用し、業務の透明性を向上。
経理部門の人材に求められるスキル
一般的な例ではありますが、経理に必要なスキルを簡単に表でまとめてみました。
| スキル | 内容 |
| 必須スキル | 基本的な会計知識、財務計算能力 |
| 法律知識 | 税務知識、労務関連の基礎 |
| ITスキル | 会計ソフトの操作、クラウド経理ツールの活用 |
| 推奨資格 | 日商簿記2級以上、税理士(科目合格含む)、公認会計士(1次合格含む) |
| その他 | コミュニケーションの高さや正義感の強さ、細かな作業が得意など |
会計に関する知識を持っている事が一つの要件になりますが、経理を始めて行う段階で絶対的に資格を保有している必要はありません。とは言え一つのスキルの判断材料として、日商簿記2級クラスの知識を持つことはポイントになるかと思います。
他にも労務や税務の知識を持っていると経理にとって重要な点となりますが、資格で考えるとファイナンシャルプランナー2級以上の資格を持っていると、最低限の知識があるという判断材料になるかもしれません。
外部サービスの活用と最適な運用方法
ここまでご覧いただいたように、すべての経理業務を社内の人員だけで対応するのは、リソースやコストの面で大きな負担となるため、大変です。そのため一部の業務を外部サービスを活用することが有効です。
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の活用
経理業務の一部を外部の専門業者に委託することで、効率化を図ります。特にBPOには、ある程度の知識が必要かつ、業務的にルーティン化しやすいものをお願いすることで、採用や教育コストに比べて、安価に安定した業務成果を期待できます。
- アウトソーシングのメリット
- 業務負担の軽減
- 専門家による正確な処理
- 最新の法改正対応が可能
- 委託可能な業務例
- 記帳代行
- 給与計算
- 税務申告
クラウド会計システムと専門家の連携の注意点
外部のコンサルティングとクラウド会計ツールを共有し、リアルタイムでアドバイスを受ける体制を構築します。
システムと会計双方に詳しい経理担当者がいる中小企業はあまり多くないかと思います。そういった場合、専門家に依頼することで、自社にあったシステムの選定から運用準備、運用開始後は日常業務のサポートなど幅広く受けることが期待できます。注意点として、こういった専門家、特に税理士への相談を考えている場合は、特定のクラウドシステムと提携していないかもポイントになります。特定のシステムと提携している場合は、キックバックのような仕組みがあったり、税理士自身の効率化のみを考えている可能性が高く、本当に自社に適したシステムを紹介してくれない可能性もあるためです。
まとめ
経理業務の効率化、ITツールの活用、人材育成、外部サービスの活用を通じて、経理部門の強化を図ることができます。本記事で紹介したポイントを実践することで、業務の精度向上とコスト削減が可能になります。貴社の経理体制を最適化し、持続可能な経営基盤を築きましょう。
弊社は最終的なゴールを自社での経理業務完結、「経理の内製化」とする会社を全面的にサポートします。経営基盤の構築段階や内部統制の強化といったどのようなフェーズであってもサポートも可能です。
業務フローの見直しや経営者にとって有用な管理会計の構築、既存のシステム利用はもちろん、新たなICTの導入についても一緒に行います。また既存社員の育成や、新たな人材採用に必要な募集要項作成から面接に至るまで、ワンストップでサポート致します。是非ご相談ください。