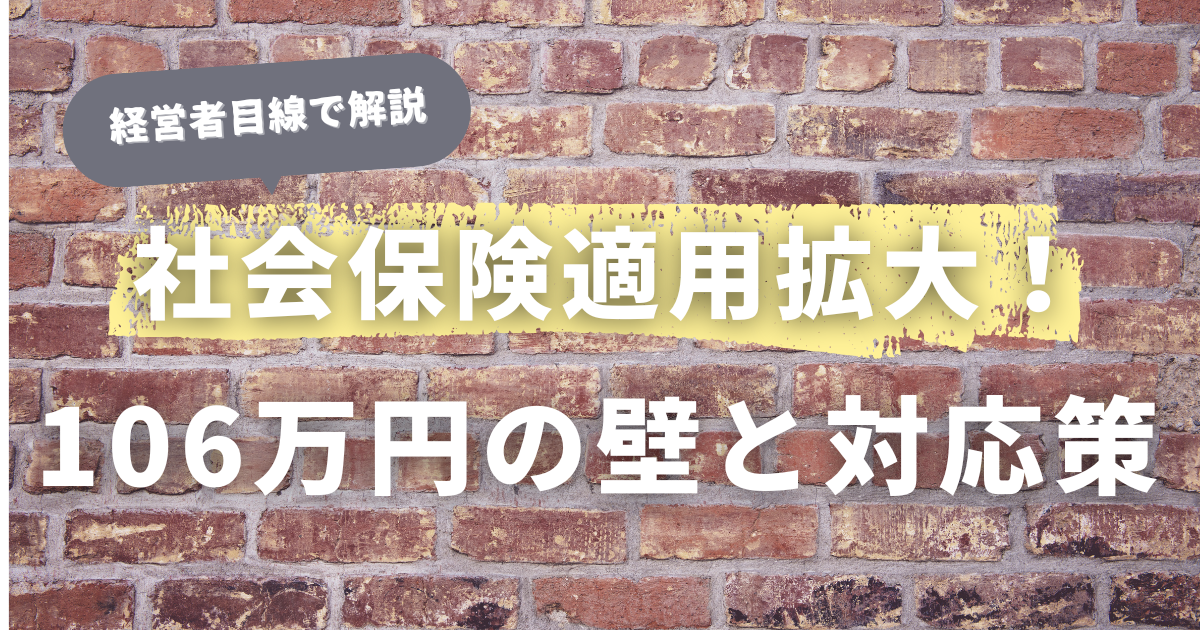問題提起:
2024年10月から、従業員50名超の企業において社会保険の適用範囲が拡大します。この改正により、人件費の増加や労務管理の負担が避けられず、多くの経営者が頭を悩ませています。経営にどのような影響を与え、どのように対応すべきか、解決策を見つけることが急務です。
記事を読んでわかること:
本記事では、社会保険適用拡大の背景と具体的な基準、経営への影響を整理します。さらに、コスト管理や運営効率化の方法、外部専門家の活用による解決策について詳しく解説します。
記事を読むメリット:
改正に伴うリスクを正確に理解し、効率的な対策を講じるヒントを得られます。この記事を読むことで、企業運営に役立つ知識と具体的なアクションプランが手に入ります。
はじめに
近年、社会保険の適用拡大が深刻な経営課題として注目されています。経営者にとって、これが意味するのは単なる費用負担の増加だけではありません。人員管理、労務手続き、そして長期的な経営計画への影響が複雑に絡み合い、会社経営に大きな変化をもたらす可能性があります。
本記事では、社会保険適用拡大の背景とその詳細な基準を整理し、経営者が直面する課題とその具体的な解決策について掘り下げていきます。さらに、外部専門家の活用方法についても言及し、効率的な対応策を提案します。
いつから始まる?社会保険の適用拡大
社会保険適用拡大は、経営者にとって避けて通れない課題です。特に2024年10月からの適用範囲の拡大が経営に与えるインパクトは大きく、今まで社会保険の加入義務に関して正社員以外は気にする必要がなかった規模会社が、対象になってしまう事があります。まずは適用基準と経営面での影響を詳しく解説します。
原則的な適用範囲
まずは現行の社会保険の適用範囲を確認します。
原則、正社員が全員加入すべき対象である事は周知の事実であるかと思いますが、短時間労働者(パートタイマーなど)も一定の要件を満たすと社会保険の被保険者となります。
その条件は労働状況として
- フルタイムで働く従業員の1週間の所定労働時間の4分の3以上
- 1月の所定労働日数がフルタイムで働く従業員の4分の3以上
この二つを満たす場合になります。
また年間で130万を超える収入がある場合も社会保険の被保険者の対象となります。
改正による適用範囲の拡大、106万円の壁とは?
上記に加えて、段階的に以下の要件に当てはまるパート・アルバイトの従業員に関しても適応対象となりました。
- 週の労働時間が20時間以上
- 月収が8万8,000円以上(通勤手当を除く)
- 継続して2カ月を超えて雇用される予定である
- 学生ではない
対象は2022年10月から、従業員数101人~500人の企業等で働くパート・アルバイト、そして2024年10月から、従業員数51人~100人の企業等で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
※月収が8万8,000円以上というのが、年収に直すと約106万円となるため、106万の壁と言われる所以です。またこの月収の計算上には通勤手当は含まれませんが、社会保険の金額を算定する標準月額報酬の計算には通勤手当は含まれます。
2024年10月改定が経営面に与える影響
社会保険適用範囲の拡大により、50名超の従業員を抱える会社はもちろん、多くのパートスタッフ支えられている会社においても、以下のような問題に直面すると考えられます。
人件費の増加
社会保険料は事業主と労働者の双方が負担しますが、事業主側の負担増が特に大きな影響を与えます。今まで対象とならなかったパートタイマーのスタッフも社会保険の対象となり、会社が負担するべき社会保険の対象人数が増えることはもちろん、給与総額が上がると比例して保険料負担も増えるため、経営計画への影響が避けられません。概算ではありますが、新たに対象となるスタッフの給与にプラス15%前後の社会保険料がかかると考えましょう。またこのほか最低賃金の上昇による影響も併せて考える必要があるかもしれません。
労働力の不足と雇用契約の見直し
労働条件を変更する必要がある場合、従業員との十分な話し合いや合意形成が求められます。パートタイムで働くスタッフの中には社会保険の扶養の範囲内で働きたいと考える方も多いかと思います。106万円の厳格化により、退職や労働時間の減少の申し入れが行われる懸念があり、労働力の不足に悩まされることもあるかもしれません。
労務管理の複雑化
社会保険加入者の人数が増えれば、入退社の手続きの回数が増えるのはもちろん、勤怠管理がより複雑化し、労務管理業務全般の負担が増大します。特に、多様な働き方に対応する場合、従業員ごとに適用基準を確認する必要があります。
コスト負担増への対応策
ではここからはこれらのコスト増に対応すべく具体的な対策を考えたいと思います。
運営効率化の重要性
コスト負担増に対応するためには、会社全体の運営効率化が不可欠です。これにより残業時間の軽減などを図り、コスト削減に繋がります。以下に具体的な方法を挙げます。
シフト管理の最適化
労働時間の過不足を防ぐために、ICTツールを活用したシフト管理システムを導入することが効果的です。例えばRelix勤怠などの勤怠管理システムを使う事が有効です。
業務プロセスの見直し
手作業で行っている事務作業を自動化し、時間とコストを削減します。特に事務作業は一度俯瞰的に業務内容を確認したり、ExcelやWordの使い方を工夫するだけで、業務の効率が劇的に改善する事もあります。またマネーフォワード【マネーフォワード クラウド】やfreee会計【freee会計】などの会計ソフトや弥生給与 Nextなどの給与計算ソフトを導入することで、手間を大幅に削減できます。
人員マネジメントの強化
適切な人員管理は、コスト削減と効率的な運営の鍵です。具体的には以下の方法が挙げられます。
パートタイム職員の労働時間調整
社会保険の適用基準を満たさない範囲での労働時間設定を検討します。ただし、適用回避を目的とした調整は、労働基準法違反になる可能性があるため注意が必要です。しっかりと対象者と話し合って、労働時間の調整をしましょう。
職員研修の実施
職員のスキルアップを図ることで、少人数でも効率的に運営できる体制を構築します。特にITリテラシーやPCスキルの向上はICT化を進める上で重要なスキルとなるため、会社全体の取り組みとして職員研修の一環に取り入れることがとても有用です。
外部専門家の活用
今回のような社会保険適用拡大への対応に限らず、外部専門家の活用を行う効果的です。主なメリットは以下のとおりです。
最新の法改正情報への対応
労務や税務に関する法律は頻繁に改正されるため、日々の業務に追われるスタッフが最新知識を認識するのは中々難しい場合があります。専門家の助言を得ることで迅速かつ正確な対応が可能となります。
煩雑な手続きの代行
社会保険加入手続きや給与計算を代行することで、管理者の負担を軽減します。またプロの業務であればミスも少なく、特にスタッフの生活にも関わる給与はセンシティブなものであるため、信頼関係を崩さないためにも外部委託が有用です。
コストの見える化
他の業務と並行して事務業務などを行っていると、中々個別の工数管理を行う事が難しいかと思います。結果としてどれくらいの労力・コストをかけているのか実際の状況が見えなくなることは経営判断に少なからず影響を与えます。一方で外部に業務を委託することで、労務管理にかかるコストを明確に把握しやすくなるというメリットが生じます。「給与の範囲内で行ってくれるスタッフが居れば、外部に出すのは単なるコスト増だろう!」という反論もあるかと思いますが、必ずしもそうとは言い切れません。社内のスタッフが本来やるべきことに割ける時間を増やすことて、最終的に残業代を含めたコスト削減や売上の増加に繋がる可能性もあるためです。
改正に振り回されず効率的な経営を行うために
社会保険適用拡大は、経営者にとって避けられない課題ですが、適切な準備と対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることができます。運営効率化や人員マネジメントの強化、外部専門家の活用を通じて、持続可能な経営を実現しましょう。
弊社は社内だけでは難しい、「DX推進」をお手伝いします。今回ご紹介したような法令の改正に対応した内部統制からシステムの設定、社内での定着化まで全面的なサポートも可能です。
手書きからの脱却はもちろん、Excel管理からシステムに移行したい、もっと効率的な業務に変更したいなど、業務フローの見直しレベルから経営者にとって有用な管理会計の構築まで幅広くお手伝いします。また最終的に自社で自走できる形を構築すべく、既存社員の育成や、新たな人材採用に必要な募集要項作成から面接に至るまで、ワンストップでサポート致します。是非ご相談ください。